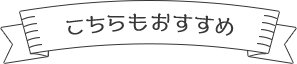公開日:2024/10/31
給与以外の収入源として、家計にとって大きな役割を果たすボーナス。しかし、ボーナスの額面はわかっていても、手取りがいくらになるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
当記事では、ボーナスの手取り金額を計算する方法について解説します。ボーナスの手取り金額を把握したうえで、有効に使うためにお役立てください。
ここからは、具体的な手取り額の計算方法について解説します。基本の計算式は下記のとおりです。それぞれの税金や保険料の算出方法について見ていきましょう。
<ボーナスの手取り額の計算式>
ボーナスの手取り額=支給額−(所得税+健康保険料(+介護保険料)+雇用保険料+厚生年金保険料)
所得税の税額は、ボーナス額面から社会保険料を差し引いた金額に、所得税率をかけて計算します。所得税率は、ボーナス支給月の前月の給与から社会保険料を控除した金額から算出します。
所得税率を調べるには、国税庁が毎年公表する「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参考にしてください。
<所得税の計算式>
所得税=(ボーナス額面−社会保険料)×所得税率
参照
健康保険料は、額面のボーナス(1,000円未満切り捨て)に健康保険料率をかけて算出します。健康保険料率は、加入している健康保険組合や勤務地により異なるため、保険料率が知りたい場合は、加入している健康保険組合に問い合わせましょう。健康保険料は勤務先と折半するため、計算した保険料が4万円なら支払う金額は2万円です。
<健康保険料の計算式>
健康保険料=ボーナス額面(1,000円未満切り捨て)×健康保険料率÷2
雇用保険料は、ボーナス額面(1,000円未満切り捨て)に雇用保険料率をかけて算出します。雇用保険料率も年度や事業種によって異なるため、厚生労働省のホームページや労働局などで確認しましょう。
<雇用保険料の計算式>
雇用保険料=ボーナス額面(1,000円未満切り捨て)×雇用保険料率
参照
厚生年金保険料は、ボーナス額面(1,000円未満切り捨て)に厚生年金保険料率の18.3%をかけ、勤務先である会社と半分ずつ負担します。なお厚生年金保険料率は、2004年から段階的に引き上げられ、2017年に引き上げが終了。2024年時点では18.3%で固定されています。
<厚生年金保険料の計算式>
厚生年金保険料=ボーナス額面(1,000円未満切り捨て)×厚生年金保険料率(18.3%)÷2
介護保険料は、第2号被保険者(40歳以上64歳まで)の場合、ボーナス額面(1,000円未満切り捨て)に介護保険料率をかけて算出します。介護保険料率は、加入している医療保険により数値は異なるので注意が必要です。第2号被保険者で健康保険に加入している場合、勤務先と半分ずつ負担します。
<介護保険料の計算式>
介護保険料=ボーナス額面(1,000円未満切り捨て)×介護保険料率÷2
これまで紹介してきた計算方法をもとに、ボーナスの手取り額をシミュレーションしてみましょう。なお、下記はあくまでシミュレーションですので、詳細な条件などによって結果は異なります。
ボーナス額面40万円のAさんの手取り額についてシミュレーションしてみます。条件は下記のとおりです。
<ボーナス額面40万円のAさんの条件>
なお、所得税率は扶養家族0人のため4.084%、雇用保険料率を0.6%で計算すると、ボーナスから天引きされる税金や社会保険料の額は下記のとおりとなります。
■ボーナスから天引きされる税金や社会保険料
| 税金・保険料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 所得税 | 1万3,926円 |
| 健康保険料 | 2万円 |
| 雇用保険料 | 2,400円 |
| 厚生年金保険料 | 3万6,600円 |
| 介護保険料 | 0円 |
<Aさんのボーナス手取り額の計算式>
手取り額32万7,074円=額面40万円−(所得税1万3,926円+健康保険料2万円+雇用保険料2,400円+厚生年金保険料3万6,600円+介護保険料0円)
ここから、Aさんの手取り額は32万7,074円ということがわかります。
ボーナス額面50万円のBさんの手取り額についてシミュレーションしてみます。条件は下記のとおりです。
<ボーナス額面50万円のBさんの条件>
なお、所得税率は扶養家族2人で2.042%、雇用保険料率を0.6%で計算すると、ボーナスから天引きされる税金や社会保険料の額は下記のとおりとなります。
■ボーナスから天引きされる税金や社会保険料
| 税金・保険料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 所得税 | 8,610円 |
| 健康保険料 | 2万5,050円 |
| 雇用保険料 | 3,000円 |
| 厚生年金保険料 | 4万5,750円 |
| 介護保険料 | 4,550円 |
<Bさんのボーナス手取り額の計算式>
手取り額41万3,040円=額面50万円−(所得税8,610円+健康保険料2万5,050円+雇用保険料3,000円+厚生年金保険料4万5,750円+介護保険料4,550円)
ここから、Bさんの手取り額は41万3,040円ということがわかります。
ボーナスとは、固定給が支払われている従業員に対して、企業が毎月の給与とは別に支給する報酬のことです。その金額には、額面(支給額)と手取り額の2つがあります。
・額面(支給額)
額面(支給額)とは、会社が従業員に支給する金額で、基本給や職位、勤続年数などの要素をもとに算定するものです。支給額は会社によって異なります。
・手取り額
手取り額とは、額面(支給額)から社会保険料や税金を差し引いた、従業員が実際に受取る金額です。
ボーナスの手取り額は、額面(支給額)の約7〜8割程度になるのが一般的です。たとえば、ボーナスの額面(支給額)が100万円の場合、手取り額は約70万円になります。
ここからは、ボーナスの手取り額の計算に必要な税金や社会保険料について見ていきましょう。ボーナスから差し引かれる税金や社会保険料には、「所得税」「健康保険料」「雇用保険料」「厚生年金保険料」があり、40〜64歳までの方には「介護保険料」も含まれます。1年間に納めた税金と社会保険料については、源泉徴収票から確認が可能です。
なお、会社員の場合、毎月の給与からは住民税も差し引かれますが、住民税は前年度の所得をもとに決定し、支払いの概算額を12ヵ月で割って毎月の給与から控除されますので、ボーナスの場合は控除されません。税金や社会保険料の種類は下記のとおりです。
所得税は、収入から医療費控除や配偶者控除などの所得控除を差し引いた金額に対して課税される税金です。所得税の税率は、収入金額や扶養家族の人数によって異なり、扶養親族が多いほど税率は低くなります。
健康保険料は、病気やケガの治療、妊娠・出産などに備える公的な保険の運営のために徴収される保険料です。健康保険料は会社員の場合、会社と本人の双方が半額ずつ負担します。健康保険の運営主体は全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合の2種類があり、地域などによって保険料率は異なります。
雇用保険料は失業や育児休業、介護休業などの際に給付される雇用保険の運営のために徴収される保険料です。雇用保険料は会社員の場合、会社と本人の双方で負担しますが折半ではありません。事業内容や時期により異なりますので注意が必要です。
厚生年金保険料は、老後の生活を支える公的年金制度を運営するために徴収される保険料です。保険料率は住んでいる地域にかかわらず一定で、2022年度の保険料率は18.3%(ただし、厚生年金基金加入員は13.3%〜15.9%)です。会社員の場合は、健康保険料と同様、会社と本人の双方が半額ずつ負担します。
介護保険料は、介護保険制度を支えるために徴収される保険料です。40歳以上の方が被保険者となって保険料を納付します。40歳以上64歳までを第2号被保険者、65歳以上を第1号被保険者と呼び、介護が必要な方に費用やサービスが支給されますが、介護を受けられるサービスの要件はそれぞれ異なります。

| 年会費 | 無料 |
|---|---|
| 国際ブランド |
|
| 種類・機能 | クレジット/WAON/キャッシュカード |
| たまるポイント | WAON POINT/電子マネーWAONポイント |
| ご利用可能サービス | AEON Pay/Apple Pay/イオンiD/家族カード/ETCカード |
ボーナス払いとは、クレジットカードの支払いをボーナス時期にまとめて支払う方法です。ボーナス払いを利用すると、カードの利用代金は、ボーナス月といわれる月の翌月にまとめて銀行口座から引落とされます。ボーナス払いは通常の1回払いと同じく、手数料がかかりません。また、ボーナス月まで支払いを先延ばしできるため、収支に余裕のある月まで支払いを延ばすことができます。
「イオンカードセレクト」は、ボーナス払いが可能なのはもちろん、イオン銀行キャッシュカード、クレジットカード、電子マネーWAONという3枚のカードが1枚にまとまったカードです。ボーナス払いでまとめ買いをしたいときにはイオンカードで支払えば、ポイントをためることもできます。
ボーナスは会社員にとって年間の大きな収入源であり、計画的に利用することで、生活の充実や将来の備えに役立てることができます。税金や社会保険料が引かれることを考慮して、ボーナスの手取り金額を計算しておき、「旅行や趣味などの楽しみに使う」「住宅や車などの購入資金に使う」「老後の備えのために貯蓄する」など、ベストな使い道を考えてみてはいかがでしょうか。